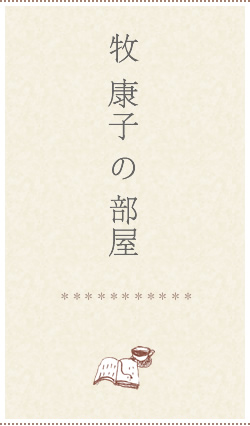年賀状 第Ⅲ回 -牧 康子-
第Ⅲ回
その年も十二月に入るとすぐ、史絵は張り切って年賀状の準備にとりかかった。年に一度の大仕事だ。まず、名簿の整理をする。名簿には、その年、年賀状を出した人、いただいた人のしるしをつけてあるから、それを目安に、出す人を決める。 十二月に入るか入らないうちに、喪中欠礼状が何枚か届く。年々その枚数が増えてくる。以前は両親の訃報が多かったが、この頃は、夫や兄弟、そしてその人自身の訃報に代わってきていた。喪中の人には黒丸しるしをつけ、亡くなった知人達は、残念ながら赤線を引いて消した。そうして史絵は、出す人の枚数を確認し、郵便局へお年玉付き年賀状を買いに行った。 いよいよ、年賀状書きが始まる。宛名も文面も、全部自分で手書きにする。絵を描ければ、庭の花のスケッチでも添えたいところだが、それは不得手だった。 翻訳の仕事をしていた頃は、もっぱらパソコンを使って原稿を書いていた。でもプライベートな手紙は、その頃もいつも手書きにしていた。特に年賀状は、新年の大切なご挨拶だから、宛名や文面を印刷ですませるのは、失礼だと思う。 文面は、出す人に合わせ、自分の近況を書き綴る。近況と言っても、時々腰や膝が痛むとか、目がかすむとか、マイナスイメージのことは書かない。春に向けて準備している花の種や、球根のこととか、気に入っている音楽や本の感想とか、あたりさわりのないことにとどめる。池田への年賀状は、庭のバラのことを中心に、ラブレターのような気分で、ていねいに綴った。 十二月十五日の年賀状投函開始日に、史絵は書きあげた七十枚ほどの年賀状の束を、郵便局の窓口まで持って行った。池田への葉書は、そっと一番下に重ねた。 「今年も、森さんが一番乗りですね」 顔なじみの局員が声をかけてくる。その日から郵便ポストも、年賀状と一般の郵便物の投函口が区別されるが、やっぱり窓口のほうが安心だ。手紙好きの史絵は、便箋や封筒は気に入ったものが見つかると、あちこちで買いもとめるが、新しく出た記念切手や、シールなどの小物は郵便局でよく買う。 時々、潤平にも、日本の食品や、孫の衣類、絵本、おもちゃなどを、郵便局から送っている。息子は、「こっちでなんでもそろうからいいよ」というが、目に付くとつい買ってしまうのだ。度々出向くので、局員たちとも親しくなった。 書き終えた年賀状を郵便局へ渡してしまうと、史絵は、一仕事終えた気分で家へ戻った。 生け垣の赤い山茶花の数が、急に増えたようだ。夕方になって新聞を取り入れがてら郵便受けをのぞくと、ダイレクトメール類といっしょに、葉書が一枚入っていた。黒枠の喪中欠礼状だ。「今頃になって、どなたかしら?」と、その葉書に目をやった。 差出人は、池田寛子とある。文面を読むと、あの先輩の池田徹が、十一月末に七十四歳で亡くなったという知らせだった。息を飲んだ。年初には、あんなに元気そうに電話してきたのにと思うと、どうしても信じられない。史絵は震える指で、電話番号を押した。何かの間違いだ、きっとまたあの操縦士の声で池田自身が電話に出てくるにちがいない。 「池田でございます」と、受話器のむこうから、落ち着いた女性の声が響いた。 「あの、大学時代、池田さんにサークルでお世話になった森と申しますが……」 「はい」と、妻と思われる女性はしばらく口をつぐんでいたが、「私は、家内の寛子です。主人は腎臓を患っておりましたが、夏から急に悪化して、先月末、とうとう亡くなりました」と、静かに告げた。史絵は、啞然とした。 「お正月には、久し振りに元気な声のお電話をいただいたばかりでしたのに」 「あの頃は一時退院して家におりましたので、皆さんにそれとなく、お別れの電話していたようです。自分でも、もう次の正月は迎えられないと思っていたのでしょう」 「そうだったんですか。私、そんなこと、少しも気づかなくて」 史絵は、がっくりと力が抜けた。 それから寛子は、一言、一言、なぞるように、生前の夫のことを話してくれた。夫が病気になってから、それなりの覚悟をしてきたのだろう。声に涙は混じらなかった。 池田は六十五歳で銀行を役員退職してからは、夫婦で食事に行ったり、旅行に出かけたり、まさに悠々自適の日々を過ごしていたという。 「それまで主人は、仕事、仕事でしたから、久し振りに新婚時代のように、いつもいっしょに楽しんでいました。子供みたいに、ここへ行こう、あそこへ行こうって。でもほんのいっときでしたけれど」 寛子は、小さな笑い声さえ漏らした。ところが池田は腎臓を悪くして、五年前から人工透析を受けなければならなくなった。週に三日の病院通いが日課になったが、それでも寝込むことはなかった。だが昨年から合併症があらわれて、めっきり体力が衰え、入退院を繰り返し、車椅子生活になったという。 確かに車椅子では、気軽に会おうとも言えなかったのだろう。史絵は正月の池田のそっけない電話の切り方も、納得できる思いだった。 「最期は、苦しむこともなく、眠るように安らかに亡くなりました」 「そうだったんですか。せめてものご最期でしたね。ご愁傷様でした」 史絵は、予想もしていなかった話に、気の効いたお悔やみの言葉も見つからず、そういうしかなかった。 「主人が、もう危なくなった頃、わけのわからないことを口走ったんです。どこかにヘビがいないかなあ。ヘビにかまれれば、苦しまずにあの世に行けるのにって。うわごとかと思ったんですが、正気で何度もそう言うんです。どなたに伺ってもわからない。森さん、何かお心当たりはありませんか?」 寛子が突然質問した。史絵は、あの『星の王子さま』のヘビの話だと思いあたった。物語の中の王子さまは、月の色をした指のように細いヘビに噛まれて、倒れるのだ。池田は、最後の最後になって、学生時代に演じたあの童話を思い出したに違いない。寛子にかいつまんでその話をした。 「人って、亡くなる前には、若い頃のことを思い出すんですねえ。その童話は、主人の本箱の中にあったと思います。私もぜひ読んでみます」妻は、納得がいったようだった。 「ずっと気がかりだった疑問が解けました。お電話、ありがとうございました」と、静かに電話が切られる。史絵は、受話器から、池田の家の線香の匂いまで伝わってくるような気がした。 史絵もそっと受話器を置くと、しばらく手を合わせて池田の冥福を祈った。もう二度と、池田から年賀状が届くことも、せっかく書いた自分の年賀状を読んでもらうこともないのだと思うと、涙が頬をつーと流れた。 寒かったが庭へ出て、史絵は夜空を見上げた。澄み切った空では、星がいくつも美しく瞬いていた。 飛行士だったサン・テグジュペリはフランス軍の飛行中隊長として、四十四歳のとき、コルシカ島沖合で行方不明になったままだという。サン・テグジュペリも、飛行士役を演じた池田も、そして「星の王子さま」を演じた夫、江守も、今はそれぞれこの空の星に住んでいるのだろう。 そう考えると、史絵には、夜空の星のきらめきが、とても親しいもののように感じられた。「いつか私も、あの星々の住人になるのだ」と思うと、自分が死ぬことが、なんだか怖くなくなってきた。 史絵はスートールを深くかきよせ、じっとそこにたたずんでいた。お隣からは、子供達のにぎやかな声が聞こえてくる。そのお宅も、お年寄りの一人暮らしだ。都会暮らしの常で、挨拶を交わす程度のつきあいしかしていないが、近くに住む娘や孫たちが毎日のように遊びに来ているらしい。ふだんは「煩わしいことがなくて、一人暮らしが一番だわ」と思っていたが、その夜ばかりはちょっとうらやましかった。 テーブルに置きっぱなしにした携帯電話の着信音が響いた。コペンハーゲンの潤平からだろう。この頃いつも息子は携帯にかけてくる。史絵は気を取り直して家へ上がると、携帯を耳に当てた。やっぱり息子からだった。 開口一番、「年末の人事異動で、僕、来年春には東京へ戻れることになったよ」と告げる。 「まあ、よかったわね」史絵は思わず笑顔がこぼれた。 「その家で、いっしょに暮らしてもいいかな? そろそろ母さんを一人暮らしさせるのも心配になって来たし」と、うれしいことをいってくれる。 「もちろんよ。楽しみだわ」史絵は、二つ返事で承知した。 潤平達の新婚時代は別居していたから、潤平の妻や孫達といっしょに暮らすのは初めてだ。そのうちよく世間で聞く、嫁姑のトラブルが出てくるかもしれないが、そういうことはそのとき考えればいいと思った。 春からこの家も、お隣のように孫達が走り回るようになるだろう。それまでに家の中を片付け、模様替えもしておいたほうがいいかもしれない。史絵は久し振りに心を弾ませながら、携帯を置いた。 来年の年賀状には、書くことが葉書からあふれそうだ。 (了)