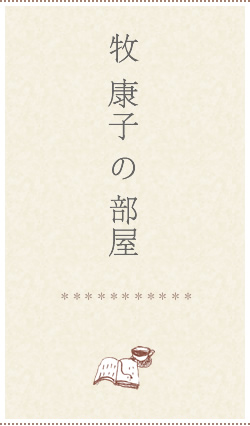年賀状 第Ⅱ回 -牧 康子-
第Ⅱ回
史絵は自分の話ばかりしていたことに気づいて、年賀状にはずっと何も書かれていない池田の近況を訊ねた。 「池田さんこそ、今、どうしていらっしゃるんですか?」 「今は、家でよくLPの古いシャンソンをかけている。ダミアの『暗い日曜日』とか、グレコの『パリの空の下』なんか、何度聴いてもいいね。古いフランス映画のDVDも観ている。そうそう『星の王子さま』もこの前読み返したよ。 確かに電話の向こうには、聞き覚えのあるシャンソンが低く流れている。池田は、相変わらずフランス趣味に浸っているようだ。この分では、銀行の仕事は、もうリタイアしたのだろう。 「そうだ、きみにひとつ知らせておかなくてはいけないことがある」 「なんでしょう?」 「江守が、去年、肺がんで亡くなった」 「えっ!」史絵は思わず声をあげた。離婚以来、江守とは会ったことも、電話をしたこともない。そのママと再婚して、子供がいるとは聞いていた。 さっと全身の血の気が引いた。別れた夫だが、何年かはいっしょに暮らした相手だ。今は自分のいきがいになっている潤平を授けてくれた男だ。亡くなったと聞いて、足もとが崩れていくような喪失感を覚えた。 「きみにはもう関係ないと思うが、息子さんには血のつながった父親だ。江守から連絡先を聞いていたから、僕が、コペンハーゲンに電話した」 池田は、史絵の動揺には気付かず、淡々と続ける。 「潤平はなんて?」史絵は受話器を握りしめた。 「帰ることはできないが、向こうで手を合わせますって、静かに受け止めていた。母をよろしくお願いしますとも言われた」 「そんなことがあったんですか」 「僕と江守は友だちだったから、たまには連絡を取り合っていた。彼はいつもきみがどうしているか、心配していたよ」 「あの頃は、私も意地を張っていたのかもしれません。最近はもう思い出すこともありませんでしたが」 「いいんだよ、それで。過ぎたことなんだから、気にしなくていい」 それもあって、池田は自分に電話してきたのだろう。史絵は言葉もなかった。しばらく沈黙が続いた。でも気を取り直し、冗談交じりにいった。 「私、少しぼけちゃったのかもしれません。今度は忘れずに年賀状をお出ししますね」 池田も、史絵に江守の訃報を伝えたことで、ほっとしたのだろう。「じゃ、楽しみに待っているよ」と、ぷつんと電話が切れた。池田の声も、池田自身も、受話器の中にスーッと吸い込まれてしまったような気がした。 史絵は「久しぶりに会って昔の話でもしようか」と、池田にいわれるのではないかと、期待していたから、拍子抜けして受話器を置いた。五十年も前の片思いが、よみがえってきた。「何年経っても、合い変わらず鈍感な人なんだから」と、ちょっとふくれて。 電話を終えると、史絵は、早速、本棚を探してみた。『星の王子さま』は、フランス文学の中でも史絵の大好きな作品だった。卒論のテーマにもしたくらいだ。洋書類はもう読むことはあるまいと処分してしまったが、あの翻訳本だけは残っているはずだ。 本棚の奥から、すっかり黄ばんだ白い函入りのその本が見つかった。大学を卒業して以来、開いたこともなかったサン・テグジュペリの童話だ。 函の表にも、本の表紙にも、作者自身の手による金色の髪で、緑色のシャツとズボン姿の小さな王子さまの水彩画が描かれている。バラの花の絵も、操縦士の絵もある。 一枚、一枚、ページを繰っていくと、その物語を夢中で読み耽った若い日々が、まざまざとよみがえってくる。当時はわからなかったが、その物語を通して、サン・テクジュペリがいいたかった「愛するということ」も、理解できるような気がした。史絵はその本を、思わず胸に抱きしめた。 そのとき、また電話が鳴った。池田が何かいい忘れたのかもしれないと、史絵は急いで受話器をとった。 「はい、森です」 「森さん、元気なの? ああ、よかった」 今度も、年賀状を中止した女友だちの一人、和子からだ。 高校時代の級友だったが、毎年、印刷だけの年賀状が届くものの、それこそ何十年も会っていない。声は、その頃とほとんど変わらず、はつらつとしていた。 「あら、私の年賀状が届かなかったの?」と、和子にも池田と同じ嘘をつく。その嘘にまたこっそり苦笑する。 「今年は来なかったわよ。この年になると、年賀状をいただくと、それだけで安心するけど、途切れると何かあったんじゃないかと心配になるの。年賀状って生きている証明書のようなものなのよね」 「そうよねえ。私、書き洩らしたのかもしれない。ごめんなさい」と、史絵はちょっとうしろめたかったので、そう謝って、手短に近況を伝えた。 「和子さんは、どうしていたの?」 「主人と私の両親が次々、病気になってね」 最近まで、その看病に明け暮れていたという。その親たちも、順番に亡くなって、今は自分の九十三歳の母親だけが施設に入っているそうだ。ずっと自宅介護や病院通いで忙しくて、友人とのつきあいは年賀状を出すのが精一杯だったという。 「それはたいへんだったわね」 「私もやっと自分の時間ができたから、近いうちに同窓会でもやりましょうよ。みんなに声をかけてみるわ。あなたも絶対出てきてよ」と、和子が提案する。 「そうね、ほんとうに久し振りですものね。お互い元気なうちに会っておきたいわね」と、史絵も賛成した。 「あっ、私、母のホームへ行く時間だわ。長話してごめんなさい」 そう言って、和子は電話を唐突に切った。電話の向こうでは、彼女の暮らしを物語るように、終始、騒がしいテレビの音が聞こえていた。 池田に続いて、和子まで電話をかけてくるなんて、自分の年賀状の取りやめがこんなに波紋を呼ぶとは思わなかった。みんな自分の年賀状を読んでいたんだ、楽しみにしていてくれたんだ思うと、うれしくなってきた。この分では、ほかの人からも電話がかかってくるかもしれない。史絵は、年賀状にいつも家の電話番号も書き添えていたから。 若い人たちには、メールや、SNSなど、いろいろなコミュニケーションの方法がある。でも自分たち世代には、今や年賀状が、お互いをつなぐ重要な絆になっていたのかもしれない。だから池田とも、和子とも、何十年振りというのに、昔と変わらずおしゃべりができたのだ。 そんなことを考えもせず、去年、年賀状を出す人をしぼったことを、史絵は後悔した。次回からは、また名簿に載っている人、全員に出そうと思い直した。 例年、新年に年賀状が届くと、史絵は、一枚、一枚、ていねいに目を通す。繰り返し読んでも、見飽きることはない。それが、正月の何よりの楽しみだった。 まず見るのは、息子の潤平からの年賀状だ。家族でコペンハーゲンに赴任してもう五年、なかなか帰国の辞令が下りない。毎年、家族写真付きの年賀状を送ってくる。北欧の冬は、長くてきびしいそうだ。室内のクリスマスデコレーションを、冬中飾っている家が多いとも聞く。写真はそんな部屋で、家族そろってクリスマスの衣装を着ている。孫たちの成長には目を見張る。時折、携帯メールでも孫の写真が届くが、年賀状は別物だ。 史絵の古くからの友だちは、手書きしてくる人が多い。内容は、自分や家族の病気のことが目に付く。みんな年をとってきたのだなあと、あらためて思い知らされる。 若い知人たちは、宛先から、差出人、文面まで、全部印刷という賀状が増えてきた。飾り文字や写真付きで、賑やかなものが多い。きっとパソコンなどを使って、デザインを工夫しているのだろう。それはそれで見るだけでも楽しいが、一行でも添え書きがあると、その人の生の声が聞こえるような気がして、ほっとするものだ。 今年も「新年のご挨拶は今回限りにいたします」と書かれた年賀状が、一枚届いていた。一抹のさびしさを感じるが、それも人生のけじめのつけ方かもしれないと思う。あらためて名前を確認したら、八十歳を過ぎた知人からだった。思えばその人からは、去年もおととしも、同じ挨拶状が来ていた。書いたことを忘れて、毎年、同じ挨拶状を出し続けているのだろう。認知症になったのかもしれないと、悲しい気分になった。 お年玉付き年賀状は、一月十五日に抽選がある。史絵は、一度だけ一等賞の一万円に当選したことがある。宝くじなどとは違って、たいした金額ではないが、それでも大喜びで郵便局へ当選葉書を持っていった。「おめでとうございます」と、局員たちが立ち上がって拍手してくれた。その郵便局で、一等賞が出たのは初めてだったそうだ。 ふだんはあまり人と話すこともない史絵だが、十二月始めから、年賀状の抽選日までは、急に何十人ともおしゃべりしているような気持になる特別な一か月半だった。 (12月号に続く)