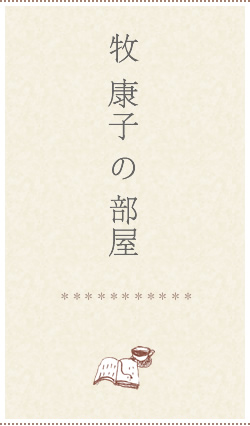年賀状 第Ⅰ回 -牧 康子-
第Ⅰ回
居間の電話が鳴った。正月には、まだセールスの電話も来ないだろう。史絵はやや緊張して受話器をとった。 「森さん、森史絵さん? 僕、フランス文学研究会にいた池田です」という。その昔、よく耳にしたあの声だ。 「まあ、お久し振りです」 「きみは元気だったんだ、生きていたんだ」と、池田の声が急に明るくなった。 昨年、史絵は古希を迎えた。その頃から、新聞を開くと、訃報欄が気になり始めた。若い頃、映画やテレビ、歌などで、楽しませてくれた有名人たちが、次々亡くなっていく。自分より若い人だったりすると、しばらくはしーんとしてしまう。 それで史絵は、自分もそろそろ終活を始めようと、思い立った。手始めは、年賀状だ。毎年迷わず名簿全員に出していたが、お世話になっている人はもちろん続けるとして、これからは賀状だけのお付き合いの人は整理しよう。そう思って、とりあえず十人ほど出すのをやめた。永年会うこともなかった人、文面が印刷だけで添え書きもない人などを、思い切って名簿から削除したのだ。 その一人が、この池田徹だった。大学卒業後は、二、三度しか会っていない。よく今まで、年賀状が続いたとさえ思う。まさかその人から、そのことでわざわざ電話がかかって来るとは考えもしなかった。 「あら、年賀状はお出ししたつもりだったのに、うっかりして」とっさに嘘をついた。 「いや、いつもいただくきみのていねいな手書きの賀状が届かないから、どうしたのかと心配になって」 池田からの年賀状は、今年も元旦に届いていた。印刷のもので、一行の添え書きもない。毎年の習慣で出したのだろうと、あえてそのままにした。返事を出さなければ、もう来年は来ないだろうと。 そうして自分も少しずつ知り合いから、フェードアウトしていけばいい。息子の潤平が、自分の訃報をみんなに知らせる前までに。まだ先のことだとは思っているが、もしかしてもうすぐかもしれなかった。 史絵は、池田の電話に、「この人を削除したのはまずかったわ」と、ひとり苦笑した。ちょっと鼻にかかった池田の特長ある声は、五十年前に聞いていたあの声と少しも変わっていない。そういうと、池田も「声は年取らないというけれど、きみの声も大学時代と同じだね」と、小さく笑った。 当時、池田は、大学のサークル、フランス文学研究会に所属する四年生だった。政経学部なのに、趣味がフランス文学で、入部したのだそうだ。 史絵が一年生の時、秋の大学祭で、サン・テグジュペリの『星の王子さま』のフランス語劇を演じることになった。配役は、先輩の池田が決めた。主役の「王子さま」は、二年生の小柄な江守真司。わがままな「バラの花」の役は、史絵の声が幼く舌足らずなので、ぴったりだと言われた。池田自身は、「操縦士」役をかってでた。 池田は着ているものも、革のブルゾンなどはおって、フランス人気取りだった。背が高く、色白で、細面の顔立ち、笑うと白い歯がこぼれる。史絵はたちまち、ぼーっとなったが、池田はその気持ちにまったく気付いてくれない。片思いだった。 サークル会員は十人ほどいたが、フランス語での芝居だったので、皆、一生懸命、台詞を覚えた。衣装も整えた。星と砂漠が舞台だったから、装置は、背景にも床にも暗幕を張った。BGMや効果音にも凝った。星の世界を象徴する音楽や、砂漠の風の音や、飛行機のプロペラが回る音を作り出すのには苦労した。 でも史絵には、池田とともにする作業はどれも楽しく、毎日ワクワクと部室に通った。大学祭で、その芝居はまずまずの成功を収めた。 池田は大学祭が終わると、滅多に部室に現れなくなった。四年生だったから、就職活動が忙しくなったらしい。そして春には念願の銀行に就職がかない、一年後、職場結婚したと聞く。史絵は落ち込んだが、どうしようもなかった。 芝居で「王子さま」を演じた江守のほうが、史絵の気持ちに気付いていて、やさしく慰めてくれた。同じフランス文学部、同じサークルで、話も合った。愛の言葉は、愛が芽生える前から、芝居の中でフランス語で交わし合っていたから、史絵はその江守と付き合うようになった。大学を卒業すると、史絵は翻訳の仕事につき、江守は新聞社に就職した。まもなく二人は結婚し、息子、潤平が生まれた。 江守は、潤平を宝物のようにかわいがってくれた。帰宅が早い日はふろに入れ、遅い日は必ずまず寝顔をのぞいた。絵に描いたような、幸せな日々だった。 でも数年ののち、離婚することになった。「星の王子さま」は、旅に出て自分の星に咲く一輪のバラの愛しさに気づくが、史絵の「王子さま」は、他の星に咲くたくさんの花々の一輪に心を移してしまった。江守は、誰にもやさしい男だったのだ。相手は年上の、カフェバーのママだった。 それを知ると、史絵は怒り狂った。夫を信じていたので、裏切られたことが許せなかった。すぐ、別れることを決めた。 池田が夫の頼みで、仲に立ってくれた。「子供もいることだし、江守も悪かったって謝っているし、やりなおせないか」と、親身に相談にのってくれたが、それでも気持ちは変えられなかった。当時の史絵は、あの物語の中の誇り高い「バラ」そっくりだったのかもしれない。何もかも遠い昔の話だった。 電話を通して史絵は、自分の簡単な近況報告をした。息子の潤平は、北欧に本社のある家具メーカーに就職し、結婚して、家族でコペンハーゲンに赴任している。だから、今は気ままな一人暮らしだ。 ずっと続けていたフランス語の翻訳の仕事は、目が疲れるのでもうやめた。原稿の締め切りに追われることも、出版社の担当者に気を遣うことからも解放されて、小さな庭の花作りに明け暮れている。もちろん、バラは大切に育てていると。 「バラの花が、自分でバラを育てているのか。それはいい」 池田は「ふふふ」と、また小さく笑った。(11月号に続く)