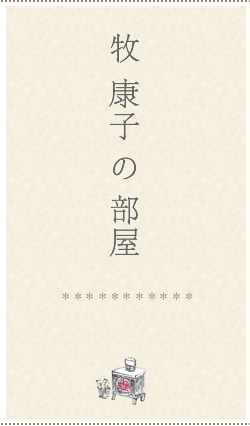チェーホフの「おじいさん」のように
◎
今年、初めて元旦に、Fさんからの年賀状が届かなかった。三日たっても、一週間たっても来ない。昨年は、宛名面は手書き、上品な絵柄の文面には、万年筆の几帳面な小さな文字で、近況が書き添えられていた。Fさんは、私の出版社時代の大先輩。今年は確か、九十歳を迎えるはずだ。現役時代から賀状のお付き合いが続いていたから、急に不安に駆られた。 私は思い切って翌朝、電話をかけてみた。Fさんは一人暮らしをしているが、足が不自由だ。ふだんは時間がかかっても、必ず電話には出てきた。でも今回は何度コールしても、応答がない。しばらくしてまたかけたが、同じだった。だんだん心配になって、夕方またかけてみた。「はい」という聞き慣れた男の声が返ってきた。ほっと胸をなでおろして「ごぶさたしております。元S社の牧康子です」と、続けた。しばらく間が開いてから、「父は昨年倒れまして、今臥せっております」と言うではないか。私は、息を飲んだ。声はそっくりだったが、確かに若い声だ。息子さんによれば、Fさんは電話にも出られない状態で、自分と妹が付き添って看病をしているということだった。手紙なら読めると言うので、お見舞い状を出すことにして、「くれぐれもおだいじになさってくださいませ」と、電話を切った。Fさんは私より一回り以上年長だったから、何時かそういう日が来ることは、頭ではわかっているつもりだった。でもFさんには、いつまでも先を歩いて行ってほしい、長生きしてほしいと願っていたのは、私の独りよがりの思いだったのだろうか。 昭和四十三年、私が新入社員としてS出版社に入社し、看板雑誌の婦人誌の生活課に配属された頃、Fさんは読み物課の働き盛りの記者だった。その頃から編集長が次々替わり、Fさんが編集長になったのは、バブルがはじけ、暮らしが厳しさを増した頃だった。私は、デスクが通した原稿は、そのまま編集長もスルーだと思っていたが、Fさんは違った。「雑誌は教科書じゃない。実用記事だってもっと読者の心に響くように」と、戻ってくる。その通りだと思い、原稿を書き直すことも少なくなかった。私のなかで、F編集長への尊敬の念が次第に高まっていった。 入社して数年、私ははたくさんの仕事を抱え、毎晩、当たり前のように残業をしていた。昼間は取材、撮影、戻って自分の原稿を書くのはどうしても夕方以降になる。F編集長も必ず残業をしていた。四十代でまさに仕事盛り、編集室の中央で、いつもデスクに向かって、部員の原稿に赤を入れたり、自分の原稿に取り組んでいた。私は、その姿に励まされた。今でこそ長時間労働が問題になっているし、在宅勤務が奨励されているが、少なくても当時の編集部では残業が当たり前だった。 忘年会シーズンがきた。編集部の忘年会は、編集長のもと、部員が全員集まった。 「婦人誌が低迷していたからこそ、私は編集長を引き受けました。順風満帆だったら、承諾していなかったかもしれない。バブルがはじけ、生活が圧迫されてきた。こんな時代だからこそ、婦人誌が見直されてきたんです。売れ行きは少しずつ回復している。こんな私についてきてくれてありがとう。これからもよろしく頼みます」というような熱いスピーチがあった。 二次会は、まだ華やかだった頃の歌舞伎町の飲み屋だった。二次会から三次会へはしごをして、お開きになったのは、十二時を回っていた。若い女性で残っていたのは、とうとう私一人になっていた。「私が送ろう。車を止めるから」と、Fさんはタクシーに手を上げ、自分が先に乗り込んで、私をドア側に乗せた。「代々木を回って所沢まで」と、躊躇なく言い添えた。 「いつも遅くまでたいへんだね」 「仕事がのろいものですから」 「いやそんなことはない。あなたはやり手だから、仕事が集中するんだよ」 そんな会話のあと、「眠たかったら私によりかかっていいよ。代々木に着いたら起こすから」と、やさしい言葉に反って私は緊張した。 「あなただけを車に乗せてみんなどう思っているだろうな。よし、明日は会社の隣の『ファースト』で、二人でモーニングコーヒーを飲もう。それを見てどんな噂がたつか、今から楽しみだな」 私は家へ帰ってからもほとんど眠れず、這うように朝早くその喫茶店に立ち寄った。いつまで待っても編集長は現れない。始業時間になったので、あきらめて編集部に行った。Fさんはデスクに向かって、何事もなかったように仕事をしていた。夕べの約束は、単に酔いに任せてのジョークだったのだ。Fさんは愛妻家としても有名だった。社内恋愛の末、結ばれたとあって、誰しもそのことを知っていた。間違っても、若い女性記者に心を動かすはずはない。私は夢から覚めた思いがした。淡い思いは、むなしくついえた。 長期に渡ってFさんは編集長を続け、その間、私も生活課のデスクに昇格し、新しいインテリア誌の編集長を任命されるにいたった。Fさんは婦人誌の編集長を退任したのちは、役員になったが、数年後、職を退いた。その送別会の席で、妻が五年前、がんで亡くなったという話を聞いた。 「最後まで、うちで女房を看取った。病院より、それを望んでいた。今まですべて女房任せだったけれど、食事づくりも、掃除、洗濯も、全部私が自分でしたんだ。息子や娘は、結婚して家を出ていた。そんな時、婦人誌時代の知識がとても役に立ったよ。庭で洗濯物を干して、パンパンと手で皺を伸ばしていると、お隣の奥さんが、さすが婦人誌の編集長をなさった方は、こういうこともおじょうずですねって、ほめてくれたよ」 Fさんは ちょっと寂しそうな笑顔を見せた。 「この前、やっと妻を偲ぶ追悼記を自費出版したんだ。元編集長としての最期の仕事としてね。今度、あなたにも送るよ」と。きっとあの細やかな文章で、妻への思いが綿々と綴られているのだろう。私はぜひ読みたいと思った。 その後Fさんは、第二の人生として、カルチャーセンターの「自分史」講座の講師の道を選んだ。私が定年退職したとき、軽い気持ちで、「聴講にうかがってもいいですか」と言ったら、「やめてください。話せなくなる」と、やんわり断られた。第二の人生は、新しい人達と、と思っていたのだろう。それからはお目にかかる機会もなく、年賀状だけのお付き合いがずっと続いた。 そのころの年賀状には、「『私はストーブの横で居眠りをしている、頭のはげた小さなおじいさんになりたいのです』というチェーホフの言葉が好きでしたが、今や、その通りになりつつある自分に苦笑しています。本望というべきでしょうか」とある。 「満州事変、学徒出陣、原水爆禁止世界大会、湾岸戦争と、自分が生きた羊年の事件から、改めて昭和・平成の歴史の重さを痛感しています。私は今年八十四歳、多分最後の年男です。今少し、昭和の語り部を努めます」という賀状もある。 「私も昨年、運転免許証を返納して、ギアを隠居生活に切り替え中ですが、第二の天職『自分史』講座の講師役だけは、最後の踏ん張りで、まだ続けております。」と、元気だった。だがFさんは、持病の脊柱管狭窄症が悪化し、二十三年間続けた自分史講師も、杖なしでは歩けなくなって退職した。 「やっと現役を卒業することができました。いつか日本の古典文学を読破したいというのが積年の夢でした。はからずも後期高齢者となった今、それが可能だと思い立ち,国文科学生の昔に返って、『方丈記』などを読み進めています」という賀状も来た。 「今年はいよいよ要介護者の仲間入りです。年をとるのも楽じゃないですね」とは、一昨年のもの。「老いとまともに向き合って、戸惑うことの多い新年です」というのが、昨年の賀状だった。 思えば大正六年に創刊された私達の婦人誌も、平成二十年に役割を果たしたと、九十一年の幕を閉じていた。Fさんは編集長として先に立ってその雑誌に力を尽くし、私達を記者の道に導いてくれた。私はその後、何人かの編集長の元で仕事をしたし、私も小さな雑誌の編集長を努めた。でも大きな声で、「編集長」と呼びたいのはFさん一人だった。 そして折々の年賀状では、老いの道の先達としてもその生き方を示してくれた。私もいやおうなくその道を歩いているが、Fさんについていけば間違いないような気がしていた。 息子さんにはFさんの詳しい病状を伺うことはできなかったが、一日も早く回復して、ストーブのそばで好きな本を読むことができるよう、今は祈るばかりだ。またいつか、年賀状が届くようにとも。 (了)