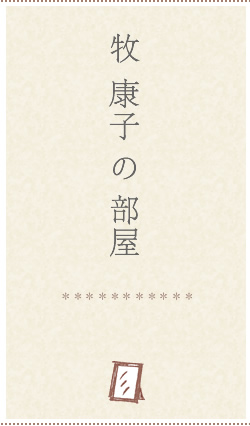母のアルバム
◎
五日前、母ハナは八十二歳で、私の目の前で亡くなった。その朝、老人ホームから「お母さまの風邪が長引いたので、病院へ入院していただきました」という連絡がきた。私は仕事を手早く片付け、その病院へ向かった。そんなことは度々あったから、驚きはしなかった。 母は四人部屋の病室のベッドにぐったりと横たわっていた。「何日も熱が下がらなくてね、今度こそもうだめかもしれないよ」と、珍しく弱音を吐く。むっとした熱のにおいもする。「だいじょうぶよ、またすぐホームへ戻れるよ」と言うと、「手を握ってくれないかい」とせがむ。母から初めてそんなことを言われたので、私はちょっと戸惑ったが、骨ばって瘦せ衰えた手をとった。「こうしていてもらうと、落ち着くよ」と、母は弱々しく握り返してきた。 その時だった。母は突然「うっ」と奇声を発し、体を海老のように丸めて、舌を出した。そしてそのまま石のように動かなくなってしまった。私は自分の目の前で起こったことの意味がわからず、ベッドのそばで固まってしまった。でもすぐにこれはたいへんなことになったと気付いて、枕元のナースコールのボタンを押し続けた。待ちかねた頃、やっと医師と看護師が、姿を現わした。「どうしました?」と、母の方へかがみこむ。 医師は慣れた手つきで、瞳孔を調べ、舌を嚙まないようにガーゼをくわえさせて、心臓マッサージを始めた。しばらく同じ動作を繰り返していたが、あきらめたように手を止め、冷静な口調で「ご臨終です」と告げる。腕時計で時間を確かめ、鄭重に頭を下げた。 私は、今の今までいつものように母と話をしていたのにと思うと、その言葉が信じられなかった。急に涙が堰を切ったようにほとばしる。拭いても拭いてもあふれてくる。母の死でこんなに取り乱すなんて、私は自分でも信じられなかった。 一時間ほどすると、ようやく涙も止まったので、早速妹に電話した。ほかに知らせる人も思い当たらない。妹は、夫と、乳吞み児をはじめ四人の子供を連れて、病院へ駆けつけてきた。顔は緊張していたが、目に涙はなかった。四人の子供の母親だという自覚が、悲しみより、勝っていたのだろう。 病院紹介の葬儀社と打ち合わせをし、遺体を斎場に運んでもらい、翌日、身内だけでささやかな通夜を行った。葬儀、火葬もすませた。そのあと、葬儀社の手で、遺骨や、遺影、位牌などのすべてが、私の小さなマンションの仮の祭壇に並べられた。妹家族は、早々に引き取っていった。 若い頃から、私があれだけ疎ましく思い、反発しつづけた母という存在は、そうしてそこにちんまりと納められたのだ。 思えば、明治四十年生まれの母の一生は、決して幸せなものではなかった。女学校卒業後、大きな商家に嫁ぎ、子供を生んだが、夫は結婚前から女を囲っていた。妾を持つことは、男の甲斐性と言われている時代だった。若かった母はそれに耐えられず、子供を渡してもらえぬまま、実家に戻ったと聞く。 その後、母は人目がうるさい郷里を離れて上京し、私と妹の父である材木商の男と再婚した。でも父も、私たち姉妹が学校へ行く頃から、女遊びに走るようになり、家へもあまり帰らない。さすがに母は「もう子供は手放せない」と、我慢に我慢を重ねたという。 母の愚痴の吐け口は、すべて私だった。「女同士だからわかるだろう」と、次から次へと繰り言を述べ立て、私をがんじがらめにする。私はそんな母を、頭では気の毒だと思ったが、心では疎ましく、何とか母のもとから逃げ出したいと思っていた。父のことは、とうから見限っていた。 夫に生活のすべてを左右されている、母のような女にだけはなりたくない。とにかく自立したい、自立すれば自分の好きな生き方ができると、勉強にも、職探しにも励んだ。そして念願の出版社に就職。経済的に一人暮らしができるようになるやいなや、実家を飛び出して、アパートを借りた。そこは狭くて日も当たらない北向きの部屋だったが、私には楽園だった。 妹は年下の優しい男と職場結婚し、堂々と家を出て行った。そして、子供を四人生んだ。その頃、母はようやく父と離婚し、妹のもとで孫の面倒を見ながら暮らすようになった。でも安らかな日々は数年も続かなかった。母は心臓の病気に倒れ、長い入院生活を送った後、病院ではもう治療法はないと、老人ホームを紹介された。 今と違ってホームは、まだ「姥捨て山」として、特別視される時代だった。母は、私といっしょに暮らしたいと望んだ。私は仕事が多忙でとても母の面倒は見られない、妹も子育て中で母の世話までは手が回らないと言って、なんとか母にホーム行きを納得させた。本音では、私は、あれだけ反発してきた母といっしょに暮らす息苦しさには、とうてい耐えられないと思ったからだ。 最初はいやがっていた老人ホーム暮らしに、母は次第になじんでいった。愚痴も出ない。ホームで、女学生時代好きだったという書道や俳句を習っているという。初めて夫からも、子供たちからも解放され、おだやかな自分の日々をすごせるようになったのだろう。私も独身のまま四十歳を過ぎていたから、老いた母に逆らう気も失せて、定期的に母を見舞う娘に変わっていった。 母の葬儀一切がすんで、明日からまた会社だと思っていた矢先、宅配便が届いた。小さな段ボール箱ひとつで、送り主の欄には母のいた老人ホームの名が記されている。品名は衣類などとなっている。ホームに置きっぱなしだった母の身の回りの物だろう。ホームには永らくお世話になったから、お礼かたがた、それらを引き取りに行かなければいけないとは思っていたが、まだその時間がとれなかったのだ。 私は、とりあえずその段ボール箱を開いてみた。八十二年も生きたのに、母が残したものはこんな小さな箱一つにだけだったのかと思うと、しみじみとした。 洗いざらしの寝間着、下着などの衣類、洗面用具などの身の回りのものは、あとでまとめて処分することにした。その下に、菓子の空き箱が一つあった。開けてみると、年金手帳や保険証などの書類、残額もわずかな貯金通帳、黄ばんだ手紙の束などのほか、桐の小箱に、私と妹の「御臍帯」と「御産毛」が宝物のように納められていた。 そして、菓子箱の下にもう一つ、古い布張りのアルバムが入っていた。表紙を開くと、厚紙の台紙に、モノクロ写真が、四隅を三角の爪でとめてある。写真の下には、母の几帳面な字で、日付と場所が書かれていた。 最初から二、三ページは、父に寄り添う和服姿の母の若い頃の写真が貼られていた。それから先は、両親と自分と妹が、仲良く暮らしていた頃の家族写真で埋め尽くされていた。 どの写真の母も、目線は子供に向いていて、愛にあふれた表情で見やっている。子供たちも、母に抱かれ、安心しきった無垢の笑顔を見せている。私は「自分たちにもこんな頃があったのだ」とあらためて目を見張った。 アルバムを繰っていると、幼い頃の思い出が、いやおうもなくページから立ち上がってくる。幼稚園にも行っていなかったあの頃、私は家の中でも、庭でも、いつも母につきまとっていた。ちょっとでも母の姿が見えないと、「母さん、母さん」と大声で家の中や庭を探し回る。妹もいつもちょこちょことついてきた。 美容院へ出かけた母の帰りが遅くなると、もう涙目の妹の小さな手を引いて、心配で胸がつぶれるような思いで坂道の上まで迎えに行った。母が、美容院のにおいをぷんぷんさせて現れると、二人で母に飛びついて行った。 そんな甘酸っぱい思い出が、どの写真からも次々とよみがえってくる。その頃は私たちにとって、母がすべてだった。母にとっても、自分たちがすべてだったのだろう。写真が出てこなければ、二度と思い出すこともなかったセピア色の日々だ。 二人が学校に入学してからの写真は、母が子供それぞれのアルバムを作ってくれていたから、母の手元にはこの一冊しか残っていなかったのだろう。 病院でも、ホームでも、母はこのアルバムを、幾度となく見返しては、幸せだった日々の思い出に浸っていたに違いない。私は目頭がジーンと熱くなってきた。 「母さん、永いこと、逆らってきてごめんね。今このアルバムをめくってみて、やっと母さんのほんとうの気持ちが分ったような気がする。これからは私、もう逃げ出さない。母さんとずっといっしょにいるから」と、母の遺影に呼びかけた。 それにしても、ホームの記念写真をトリミングした母の遺影は、あまりにみすぼらしかった。私はアルバムの中から、母が一番きれいだった頃の写真を一枚はがして、入れ替えてみた。 父が庭で撮ったものだろう。母はセーターにスカートという普段着姿だったが、庭木をバックに、カメラに微笑みかけている。カメラの横には、きっと自分たちがいたにちがいない。写真からは、母の笑い声さえ聞こえてくるような気がした。母の、私といっしょに暮らしたいという夢を遅ればせながら果たそうと、私は涙ながらに写真立ての位置を整えた。(了)