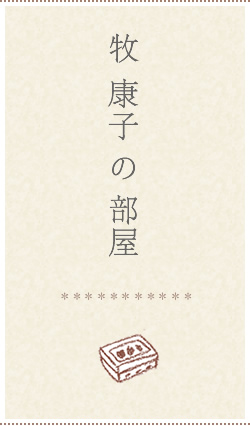母の文箱
◎
この春、二十年住んだマンションの床をリフォームすることにした。十年前に壁紙を貼り替えたが、今回はフローリングだ。業者に、家具を動かしながらの工事だから、七つあるチェストの中身を、全部段ボールに詰めておいてほしいと言われた。そこには暮らしの一切合財が収納されている。引っ越しと変わりない。でもそろそろ身辺整理を始める年代に入ったから、いい機会だとも思った。 年末から新年にかけて、 捨てた、 捨てた。 バルバラやマリー・ラフォレなどのシャンソンのLPも、豪華なオペラのプログラムも、昔からの年賀状の束も。懐かしいものばかりだったけれど、ほとんど全部処分した。荷物は半分近く減った。 その折、二十五年前に亡くなった母の遺品の鎌倉彫の文箱を、久し振りで開けてみた。上の方には、母の葬儀のあと、私がばたばたと入れた会葬者芳名録や御香典帳があったが、下の方には見逃していた古い古い資料がいくつか残っていた。母が亡くなるまで、大事に手元に置いていたものだ。 私は片付けの手を休めて、一つ一つ手に取ってみた。一番古いものは、切れ切れの奉書に書かれた祝辞。開けてみると、「野辺には秋の七草咲き乱れる心地良き今日…」で始まるその祝辞は、ていねいな筆文字で、女学校の校長への誕生日祝いが綴られていた。最後に、大正十二年十月十五日 生徒総代として母の名前があった。母には、さぞ晴れがましいことであっただろう。 次に古いものは、黄ばんだ大正十三年三月二十五日付の東京日々新聞・静岡版。その年の地元の高等女学校の優等卒業生数名の名前と顔写真が小さく掲載されていた。母の名前も写真も載っている。これも母にとっては、誇らしい記事だったに違いない。 あとは、娘時代から使っていたと思えるぼろぼろのノート一冊。和服の仕立て方、生け花の作法などが、鉛筆書きで半分ほど埋まっていた。合わせて、雑誌「主婦之友」の昭和十一年新年号附録・経本式「和服一切お裁縫全集」が保存されていた。私が生まれてもいなかった頃の付録だ。当時母は、将来、自分の娘がその出版社に勤めるようになろうとは、思いもしなかっただろう。 ほかには桐の小箱に、私と妹の「御臍帯」と「御産毛」が宝物のように納められていた。 でも驚いたのは、半紙一枚、一枚に朱の筆文字で書かれた俳句が残されていたことだ。数えたら二十枚以上あった。母が習字を得意としていたことは知っていたが、俳句を詠んでいたという話は聞いたことがない。母がそれらの句を習字の手本にしたのか、母自身が詠んだ句を朱書きしたのか、もうその真偽のほどは確かめようもない。でも俳句として鑑賞してみると、それらは、母が詠んだような気がする句もあり、内容的に違うような句もあった。でも今さらどちらでもよかった。とにかく母には大切に保存しておきたい作品だったのだろう。こんな句が並んでいた。 元旦や何事もなき日でありき 夫在りし日々の徳利に山茶花を 満開や老いたる身にもまた春が 思えば、明治四十年生まれの母の人生は、決して幸せなものではなかった。女学校を優等で卒業したまでが花の時で、あとは不幸の連続だった。卒業後すぐ大きな化粧品問屋に嫁ぎ、二人の子供を産んだが、夫は外に女を囲った。若かった母は耐え切れず、子供を置いて実家に戻った。その後上京し、私と妹の父親である材木商の男と再婚。でも二番目の夫も、女遊びに明け暮れ、子供が生まれても浮気はやまない。もう子供は手放せないと、母は我慢に我慢を重ねた。手に職もないことから、そうするしかなかったのだろう。 そんな両親のもとで育った私は、大きくなっても結婚願望はなかった。とにかく、自立すれば自分の好きな生き方ができると、勉強にも、職探しにも励んだ。そして念願の出版社に就職でき、実家を出た。逆に妹は、幸せな家庭を目指して、年下の優しい男と結婚し、子供を四人生んだ。 母はようやく父と離婚し、妹のもとで孫の面倒を見ながら暮らすようになった。私は経済的援助をした。でも安らかな日々は数年も続かなかった。母は心臓の病気に倒れ、長い入院生活を送った後、普通の暮しは無理と、老人ホームへ入所した。 朱書きの俳句は、老人ホームの趣味の会で、母が書いたものに違いなかった。 母はホームで心筋梗塞で亡くなった。八十二歳だった。発作が起きたとき、ちょうど私が見舞いに行っていたので、母は私の手を握りながら安らかに逝った。私は、いつもそばにいられなかった自分の親不孝を思って、涙が止まらなかった。 母は本当に身一つで入所したので、遺品といえるものはほとんどなかった。数枚の和服は妹の家の納戸に納め、この文箱が私の手元に残った。私は母の文箱を開けたものの、その中のものは一つも捨てられず、そのまま蓋をした。母の大切だったものは、この文箱一つだったのかと思うと、せつないような、でもあっぱれだという気にもなった。 私もいつか、このマンションを出て行く日が来るだろう。ホームに入るか、入院するか。でもそれまでは、リフォームしたこのマンションをベースに、俳句に、小説に、エッセイに、前向きに取り組んでいくつもりだ。 そのうち私も、新しい文箱を一つ用意しておこうか。そこに、初めて自費出版した小説一冊と、「童子」数冊だけをしまっておこう。いつの日か、妹や、その子供達や、孫たちが、ささやかな私の足跡を、そこに見つけるかもしれない。