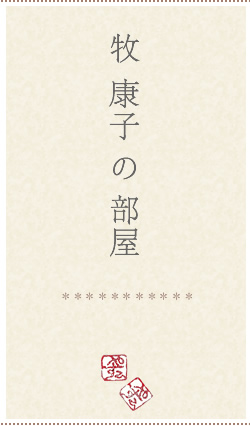鯖江で、「夢の夢こそ」の朗読劇や対談、サイン会を
2022年11月05日 [ No.117 ]
◎
三度も福井県の鯖江を訪ねるとは、思ってもいなかった。一度目は「恋話」の取材で、二度目は「夢の夢こそ」のまさかの授賞式で、三度目はなんとその朗読劇観劇と、作家・藤岡陽子さんとの対談、そして自著のサイン会をするために。 このお話しがあったのは、春まだ浅い頃。鯖江の立待公民館館長の浮山英穂氏から、「秋の『近松まつり』で、あなたの第三回近松文学賞を受賞した『夢の夢こそ』の朗読劇をします。そのあと作家の藤岡陽子さんと対談をしてくれませんか」との連絡をいただいた。 浮山館長は、私が初めて鯖江を訪れた時の案内役をかってでた方で、その後の授賞式、漫画化まで、すっかりお世話になった方だ。無下にお断りすることもできず、「プロの作家の方との対談なんて自信がないから、しばらく考えさせてください」と、言葉を濁した。夏になって、この話は立ち消えになったと思っていた頃、再度、「どうしますか。準備は着々進んでいます」と念押しされた。 私は四十年近く記者はやって来たから、取材はいいが、対談なんて初体験だ。できるかどうか不安だったが、あたって砕けろと、眼をつぶって承諾した。それから、藤岡さんに『夢の夢こそ』を送り、彼女の小説『おしょりん』も読んで、互いに質問を交わし、対談の骨子を固めていった。 「近松まつり」が近づいたころ、浮山館長から、「新型コロナウイルスの抗原検査を受けてきてください」とのメール。いよいよ本格的になってきたと、身が引き締まった。出発前日、抗原検査を受け、めでたく陰性の証明書をもらった。そして山陽新幹線に乗り、米原で特急「しらさぎ」に乗り換えて三時間余、鯖江に到着したのである。 一夜明けて、十月一日。いよいよ「近松まつり」の当日となった。鯖江は、近松門左衛門が生まれ育った町で、このおまつりも二十五回目となる。鯖江駅で、京都からいらした作家の藤岡陽子さんに初めてお目にかかり、ご一緒に会場となる立待公民館へ向かった。 まつりのオープニングは、九時からということで、公民館では館長はじめスタッフの方々は揃いの法被で、忙しそうに飛び回っている。人形浄瑠璃や、子ども文楽、近松茶会などが行われたあと、午後一時から、「しあたー近松」の皆さんによる「夢の夢こそ」の朗読劇がはじまった。 朗読劇とはいえ、舞台に主人公の史絵や、恋人の豊川、語り手の三人が並び、涙を流さんばかりの熱演をした。雨の音や、電話などの効果音も入る。文字だけの小説と違って、いきいきとした世界が立ち上がって見えた。原作者の私としては、嬉しいやら、恥ずかしいやら、感動のひとときだった。 続けて、作家・藤岡陽子さんと私の対談になった。内容はは、それぞれの経歴や小説のなりたち、小説に賭ける思いなど、質問を交わしながらの三十分だった。 その後は、藤岡陽子さんのトークショウ。彼女は、1971年、京都市生まれ。同志社大学卒業後,報知新聞社でスポーツ記者として勤務。退社後、タンザニアの大学に留学、帰国後、慈恵看護専門学校を卒業し、看護師免許取得。それから『いつまでも白い羽根』(光文社)で作家デビューという多彩なキャリアの持ち主だ。二〇一六年、鯖江の眼鏡づくりのなりたちを綴った歴史小説『おしょりん』(ポプラ社)を刊行。 この小説は、来年映画公開予定だ。トークショーでは、一時間にわたって、その経緯を手振り身振りも鮮やかに語った。 最後に、藤岡さんと私の著書のサイン会が始まった。一冊も売れないかもしれないと心配したが、それぞれ二冊とも買う方が多くて、差し出された本に、私も自分の名前を書き、落款まで押すという晴れがましい思いをした。初体験の対談もサイン会も終わり、ほっとして、私は五時前の「しらさぎ」で鯖江を後にしたのである。 福井県鯖江市は、人口約六万七千。国内シェア96%という眼鏡枠、漆器、繊維の三つが地場産業として発達。さらに市民が北陸随一の文化都市を目指して力を尽くしているさまが、この三回の旅でひしひしと伝わって来た。「近松文学賞」も、その文化活動の一環だ。私が受賞した時の特別審査員は、故藤田宜永さんだったが、募集再開の来年は藤岡陽子さんだ。 「近松文学賞」応募をきっかけに、魅力のある街、鯖江を知ったことは、私にとっては大きな収穫だった。