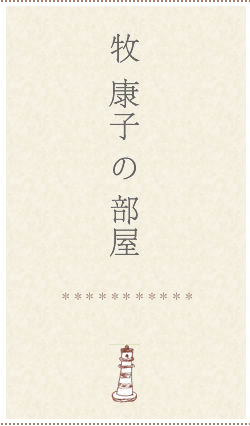『森瑤子の帽子』と、私のこと
2019年08月05日
◎
私が、作家、森瑤子さんに最後に「会った」のは、1993年7月8日、聖イグナチオ教会で行われたカトリック葬、当日だった。彼女は、前年秋、篠山紀信が撮影した写真を、友人亀海昌次が彼女の指示に従ってトリミングした遺影のなかで、オーストリッチの帽子をかぶり、赤い唇で微笑んでいた。3人の娘たちは平田暁夫が作った黒いベールのついた帽子をかぶって並び、中央にはイギリス人の夫、アイヴァン・ブラッキン氏がひょろっとした長身で立っていた。参列者は2千人に及び、生前、自身が自分の葬儀をコーディネートしておいた華やかなセレモニーだった。五十二歳という早すぎた一生でもあった。 そんなことを私が思い出したのは、今年の2月出版された、島﨑今日子氏の『森瑤子の帽子』(幻冬舎刊)というノンフィクションを、読んだためだ。この本には、五木寛之、山田詠美、近藤正臣ほか、数多の証言から、作家、森瑤子が全力で駆け抜けた彼女の一生と、日本のバブル時代が書き連ねられている。その時代は、森さんより四歳年下の私が、記者、編集者として、フルに仕事に打ち込んでいた時代と、重なっていた。 1978年、森瑤子は「情事」を書いて、三十八歳で作家になった。妻であり、三人の娘の母であること以外に何者でもない自分に満足できないでいた伊藤雅代にとって、森瑤子という自身で名付けた名前の名声と、収入は、どれほどの解放感をもたらし、自尊心を回復させたことだろう。そうして、母娘の葛藤、主婦の自立、セクシュアリティといった「女のテーマ」を誰よりも早く日本で小説にしたのである。 その「情事」を読んで、衝撃を受けた私は、それから彼女の小説を片端から読みふけった。大学時代まで、小説家を夢見ていた私は、自分の果しえなかった夢を、精力的に実現していく彼女に、託していたともいえる。 小説家と言う夢に目をつぶった代わりに、私は、出版社で、記者、編集者という立場を得た。婦人誌と実用誌がメインの会社だったから、作家と関わる機会は少なかったが、それでも記者の特権をいかして、違う形で、森さんに近づいた。 ちょうどインテリア誌の担当だったので、下北沢のお宅へ伺い、彼女がカナダの島、ノ―ウェイ・アイランドを島ごと購入したという、その島と別荘を取材したいと申し出たのだ。私はカナダ政府観光局と交渉し、ノースウエスト航空の広告とバーターで、森さんと記者、カメラマンの飛行機代を負担してもらった。その提案に森さんも快諾。そして88年、他社に先駆けて、「プラスワン」というインテリア誌に、10ページにわたる「帽子をかぶっていない森さん」と、別荘暮らしの写真を掲載し、森さんから原稿も書いていただいたのだ。 その後、広告で付き合いのあったミサワホームの広報の希望で、森さんを紹介し、三澤千代治社長との対談が実現した。その関係で、森さんは、ミサワホームが「文化人村」というプロジェクトを構想し、力を入れていた与論島がすっかり気に入り、先陣を切った形で、89年に素晴らしい別荘を建てたのだ。 夏は軽井沢の貸別荘で過ごし、86年にはカナダに島を持ったあとでの決断だった。以降、彼女は度々与論島を訪れ、五木寛之や山田詠美なども招待した。そして今は、彼女自身が生前、こんなふうにと決めた、そこの高台のガウディ風の白い墓石の墓に眠っているという。ブラッキン氏は、そこでシーサイドガーデンをはじめ、カフェも開いているそうだ。 私は、そのずっと前、ミサワホームからの話で、一度だけ与論島を取材したことがあったが、国内とは思えぬ青い海に、圧倒されたものだ。 カナダ取材後、私は森さんとのつきあいはなかったが、社の出版部からは何冊か本を出されている。葬儀には、驚きと悲しみのなかで列席した。 また森さん一家がその昔夏を過ごした軽井沢の貸別荘が、今は「涼の音(すずのね)」と言うカフェになっている。私は毎年、夏には軽井沢へ行っているので、彼女を偲んで必ずお茶を飲みに行くことにしている。 森さんは52歳で、スキルス性胃がんで早逝されたが、私も定年を控えた58歳の時、後腹膜がんで倒れた。運よく命を取り留めたので、定年後、小説を書き始めた。森さんには遥かに及ぶべくもないが、若き日の夢を、第二の人生のよりどころとしている。ようやく小さな文学賞を、いくつかいただけた。いつになるかはわからないが、今は、最期まで小説を書き続けたいと思っている。