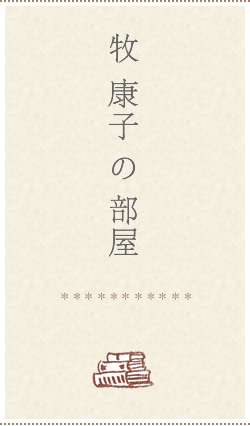久坂部羊の医療小説「悪医」に感銘
2014年10月01日
◎
「残念ですが、もうこれ以上、治療の余地はありません」と、万策尽きた外科医・森川良生(三十五歳)は鎮痛な面持ちで患者に告げる。「余命はおそらく三カ月くらい。好きなことをして、時間を有効に使ってください」と。 早期の胃がんの手術を受けた患者・小仲辰郎(五十二歳)は、十一カ月後にがんが再発して、肝臓と腹膜への転移が見つかった。森川はあれこれ手を尽くしたが、ついに使うべき薬がなくなった。悪意があって言ったのではない。副作用で命を縮めるより、残された時間を悔いのないように使った方がいいと、小仲のためを思って告げたのだ。 だが小仲は、つらい治療に歯を食いしばり、吐き気やだるさに耐えてきたのは、どんなに苦しくても、死ぬよりましだと思ったからだった。胸に激情が込み上げ、「先生は、私に死ねというんですか。治療法がないというのは、私にすれば、死ねと言われたのも同然なんですよ」と、怒り狂う。この若造の医者に何がわかるのかと。 どんな状況でも、治療は生きる希望。小仲は、突き付けられた自分の死を受け入れられず、まずセカンドオピニオンを求めて、大学病院へ駆け込むが、ここでも受け入れられない。新聞広告で、抗がん剤を専門とする「腫瘍内科」の存在を知り、入院を決意するが、前にも増して抗がん剤の副作用がきついうえに、お金がかかる。看護師から「ここの先生は患者をモルモット扱いしている」とささやかれて、退院した。 次にブログで、がんの三大治療(外科手術、抗がん剤、放射線)に次ぐ第四の治療法、「免疫細胞療法」のことを知る。それは副作用のない夢の治療法だったが、効果もなく、高額医療費を請求されるだけで、がんは肺にも転移し、胸水が貯まる。彼は命を縮める不必要な治療の矛盾にやっと気付く。万策は付きた。 最後に、小仲は、がん患者の精神的サポートをしている会のスタッフの力を借りて、ホスピスに入所し、自らの死を受け入れる。医師側の苦悩にも気付いたうえでの、静かな旅立ちだった。自分に余命宣告した「悪医」森川への、感謝の言葉をテープに吹き込んで。 この作品には、死への不安に耐えられない患者と、患者からの不信に擦り減っていく医師。それぞれの苦悶が、テクニックを労さず、ありのままにていねいに描かれていた。 私も十二年前、人間ドッグで腹部のがんが見つかり、専門病院で手術、化学療法を受けた。当時は自分ががん患者になったことに動転し、医師側の気持など思いも及ばなかった。ここに出てくる抗がん剤の名前もいくつか知っている。だからこの作品は、他人事とは思えなかった。繰り返し読んで、ラストシーンには、そのたび涙した。私の場合、今のところ、幸い再発も転移もなく過ごしているけれど。 これは、2014年、第三回日本医療小説大賞を受賞した作品で、作者が自らの外科医時代の体験を下敷きに、がん治療をめぐる医師と患者の溝を見つめている。患者が書いたがん闘病記は数々あるが、医師が書いた作品は少ない。作者は、現役医師ならではのリアリティーで、現実の医療現場を描き切っている。それだけに説得力があり、大きな感銘を受けた。 久坂部羊は、麻痺した手足を切断する医師を描いた「廃用身」(2003年)で、作家デビュー。著書には、大学病院を克明に描いた「破裂」(2004年)、医師が連続殺人鬼を追い詰める「無痛」(2006年)、治療するほど悪化する新型カポジ肉腫を描いた「第五番」(2012年)、医療ミスの闇を追及する「糾弾」(2012年)など、医師ならではの視点で、医療の問題点を鋭くついた作品が多いが、この「悪医」が一番、率直で、心に響くものがあった。 二人に一人はがんにかかると言う時代、今健康に過ごしている人にも、ぜひ一度読んでいただきたい作品だ。