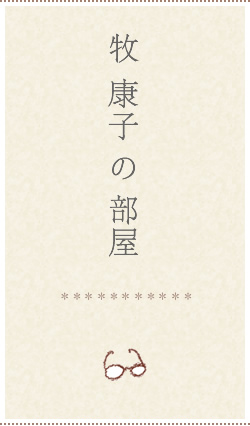夢の夢こそ -牧 康子-
◎
朝から降り続いていた冷たい雨が、夕方からみぞれになった。史絵は、こんな日は客も少ないだろうと、料理の仕込みを控えめにした。案の定、馴染みの客が二、三組帰った後は、客足がぱったり途絶えた。 そんなとき、背の高い見知らぬ男が一人、引き戸を開けた。髪は長めだが、白いものが交じっている。眼鏡をかけ、黒い革のブルゾンにスラックス、黒いタートルネックのセーターと、黒ずくめだった。マフラーだけは縞柄の温かそうな物を身に着けている。どんな職業の人か、見当がつかなかった。 「いらっしゃいませ。お飲み物は?」 「日本酒をください、熱燗で」 男は、壁に並べた日本酒の瓶の一つを指差し、マフラーをはずした。レンズが曇ったのか、眼鏡もカウンターに置いた。鼈甲ぶちのしゃれた眼鏡だ。思いのほか、やさしい目をしている。史絵は酒といっしょに、お通しの蕗味噌を並べた。お通しは季節を先がけるのが、史絵の心意気だ。自分から進んで話しかけるのは控えていたが、男は酒を飲むだけでずっと何も言わない。 「何か召し上がりますか?」 待ちかねてそう声をかけてみた。男は初めて気付いたように、手元の品書きを見て、さわらの焼き物とたたきごぼうを注文した。 「毎月のようにこの近くに来ているが、今まで気付かなかった。落ち着いたいい店だね」 「私一人でやっていますから、たいした料理もお出しできません。家庭料理の延長です」 「もう蕗の薹を使っているんだ。春の香りがする」と、男は酒をもう一本追加した。狭い店内を見回し、「花もいいな」と言う。酒の客は料理を褒めても、なかなか花にまでは目が行かない。史絵は、その男のこまやかな心遣いがうれしかった。やさしかった夫と同じ匂いを感じた。 史絵は、「花の里」という店の名に恥じないよう、花だけはいつも絶やさなかった。その日は、壺にあふれんばかりに、咲きかけの梅の枝ものを活けていた。小枝を箸置きにもしていた。 その時、二人連れのサラリーマンが入って来た。史絵はその相手にとりまぎれ、それから男に声をかけられなかった。男は静かに酒を飲んでいたが、しばらくすると勘定を頼み、席を立った。男は「また、寄るよ」と、白い歯並びを見せた。それが、史絵と豊川の最初の出会いだった。 史絵は、三年前、交通事故で突然、夫を亡くした。子供はいなかった。四十歳を過ぎた女にできる仕事はなかなか見つからない。 そんなとき、夫がよく連れて行ってくれた小料理屋のおかみが、老親の介護で店をたたむという。居抜きで店を譲るから、替わりにやってみないかと、声をかけられた。史絵は、料理だけは得意だったから、思い切って引き受けてみた。カウンター席だけの小さな店だったが、前からの客や夫の友人などが絶えず来てくれるので、細々ながら店は続いている。 そのみぞれの日以来、豊川は時おり、「花の里」に立ち寄るようになった。いつも料理は二、三品注文するだけだったが、だんだん酒量は増した。 「そんなにお酒ばかりお飲みにならないで、料理も召し上がってください。お口に合うものを何でも作りますから」 「女房と同じようなことを言わないでくれ」 豊川は、苦笑いして一品くらいは追加するが、後が続かない。すぐ酒にもどった。 「俺はもうすぐ還暦だ。息子も一人前になったし、好きな酒をひかえるくらいなら、死んだほうがましだ」と、男は投げやりな言葉をもらすこともあった。 豊川は眼鏡で名高い福井県の鯖江で、越前漆器の工房をやっていて、東京へはその商談に来るのだという。「若い頃は東京の小さな劇団で、裏方から、役者まで、なんでもやっていた。でも父親が早逝して家業を継がねばならなくなったんだ。東京に来ると、商談の後、昔の仲間に会うのが楽しみだよ」とも。男の服装は、当時のなごりなのであろう。いつしか史絵は、男の来る日が待ち遠しくなってきた。夫が亡くなって以来、ほかの男にそんなに心が動いたのは初めてだった。 やっぱり冷たい雨の夜、客足が途絶えた店の二階で、二人は結ばれた。「雨が激しくなったみたい。よろしかったら、泊まっていらっしゃいませんか」と、杯を重ねる男の手に自分の手を置いて誘ったのは史絵からだった。そういう雰囲気が男にもあった。 豊川は、長襦袢になった史絵をぐいと抱き寄せると、唇を合わせ、横たえた。手を襦袢の中に差し入れて、乳房から、腰、脚へと愛撫を続ける。ピンがはずれて、史絵の髪が放射状に拡がった。男は、襦袢の腰紐を解くと、やさしく体を重ねてきた。久しく忘れていた史絵の花が、みるみる開き、潤った。 豊川はその夜、史絵の家に泊まっていった。寝物語に、いろいろ鯖江の話をしてくれた。 「鯖江には、近松門左衛門が育った里がある。そこに近松の文楽人形が展示されている。きみは、そのお初という人形に、一重まぶたの目といい、小さなくちびるといい、そっくりなんだ。初めて店に入った時、あっと思った」と言いながら、激しく咳き込んだ。 「だいじょうぶ? 病院にはいらしたの?」と背中をさすると、豊川は「ただの風邪だ」といなす。医者が苦手なのだろう。「鯖江は良いところだから、いつか来るといい」と話を続けた。「会った時から、一度、『お初』を抱きたいと思っていた」と、乳房をまさぐりながらささやく。史絵はうっとりと男の胸に顔を埋めた。男はまた咳をした。 翌朝、豊川は眼鏡を鏡台の上に忘れて帰った。気付いて通りをのぞいてみたが、もう姿は見えない。今度来たとき返せばいいと、それ以上、後は追わなかった。史絵は、壺の花を、白い小手毬から紅い侘助椿に活け替えた。そうしたいはなやいだ気分だった。なぜか椿が一輪、ぽとりと床に落ちた。 その日以来、豊川からの連絡がふっつり途絶えた。肌を合わせたあとでは、いっそう、恋しさが募る。あの夜は、男にとっては単なる遊びだったのだろうか。史絵は、自分から電話はかけまいと決心していたのに、待ちきれずに男から聞いていた番号を押してみた。「この電話は、電源が入っていないか、電波の届かないところにあります」という機械音が空しく流れた。 深夜になって、携帯が鳴った。慌てて取り上げると、豊川の名前が表示されている。 「きみの着信に気付いたけれど、病院にいるから、すぐ出られなかった。今、看護師の目を盗んで電話をかけている。落ち着いたら、必ずまた行くよ」 いつもの低い声だった。病院のしーんとした静かさが電話を通して伝わってくる。史絵は、医者嫌いの男が入院しているということは、風邪などではなく、かなり重い病気だと察した。不安にかられた。「きっと、きっとよ」と、それ以上言葉が続かなくて、男が切るまで、携帯を握りしめていた。 それから、いくら待っても豊川からの連絡はない。史絵は、思い余ってまた電話をかけてみたが、前と同じ機械音が流れるだけだ。返信もない。男は亡くなったのだと、直感した。形見になってしまった眼鏡をぎゅっと握って、「あなたまで逝ってしまったのね」と、涙をあふれさせた。 四月半ば、史絵はどうしても豊川の生死を自分の目で確かめずにはいられなくなった。店の休みに、新幹線と特急を乗り継いで、鯖江に向かった。駅に降り立つと、桜がいっせいに花開き、街中が桜色に煙っていた。どこもかも豊川の話どおりの美しい街だった。駅前の観光案内所で地図をもらい、まず越前漆器の「うるしの里会館」に立ち寄って、豊川の工房のことを訊いてみた。 「先日、赤ちゃんが生まれたお家ですね」 「えっ、赤ちゃんが?」 「豊川さんのお孫さんですよ」 半信半疑のまま、史絵は教えられた道をたどった。なんと家の前に豊川が立っている。生きている。しかも赤ちゃんを壊れ物のように抱いている。かわいくてたまらないというふうに、目を細め、相好を崩していた。 見慣れない黒縁の眼鏡をかけ、服装も、トレーナーにジーンズという普段着だ。そこにいたのは、自分のまったく知らない男の姿だった。すぐ家から若い男女と、年配の女が出て来て、赤ちゃんを抱きとった。 物陰から見ていた史絵は、呆然とした。病院というのは、産院だったのだ。そこで豊川は、家族といっしょに孫が生まれるのを待っていたのだ。男の言葉を一つずつ思い出してみた。男は一言も嘘はついていない。騙してもいない。自分が、一方的にとんでもない思い違いをしていただけなのだ。 「ばか、ばか。こんなに客に夢中になるなんて、おかみ失格だわ」と、自嘲の涙と笑いが込み上げてきた。 史絵は逃げるようにそこを後にし、喫茶店に飛び込んだ。コーヒーを飲んで気持ちが落ち着いてから、バッグにしのばせていた豊川の眼鏡をかけてみた。度が入っているから、世の中がゆらゆらとゆがんで見える。そのゆらぎのなかに、はじめて店に現われたときの男の長身が見える。黙って酒を飲んでいる背中が見える。この眼鏡の中だけには、自分が恋した豊川がまだいた。「でも、いっときの夢だったのだわ」と、史絵はそれをハンカチにくるむと、そっと椅子の隅に残して、喫茶店を出た。鯖江の街は、春霞の中にもう暮れ始めていた。 (了)
次ページもご覧ください。
小説「夢の夢こそ」が、「さばえ近松文学賞」最高賞受賞 8月30日、最終審査の結果、応募総数458点の中から、最高賞の近松賞に選ばれた(福井新聞共催・特別審査員、藤田宜永氏)。 9月18日、「福井新聞」と、鯖江市のホームページにも掲載された。